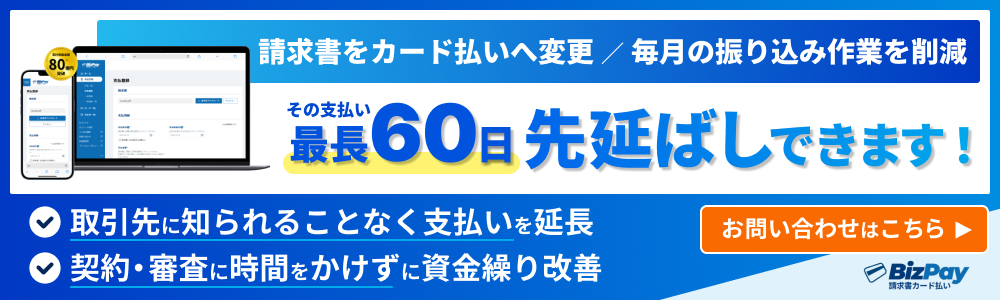スマホ決済とはスマートフォンを使用して商品の支払いを行う方法です。現金を使用せず、QRコード決済やタッチ決済などで支払いが完結します。スマホ決済は瞬時に会計を行えたり、ポイント還元やキャンペーンを活用できたりします。
しかし、「具体的にスマホ決済を利用するメリットって何?」「スマホ決済の導入や設定方法を知りたい」といった疑問が出てくるでしょう。
そこで本記事では、スマホ決済の概要から利用するメリット・デメリットを解説します。スマホ決済の導入や設定方法、利用時の注意点も解説するため、スマホ決済の活用を検討している人はぜひチェックしてください。
スマホ決済とはスマートフォンだけで支払いが完結する仕組み
スマホ決済とは、スマートフォン一台だけで支払いが完結する仕組みのことです。従来までは、現金やクレジットカード、デビットカードなどを入れて持ち歩き、店頭でそれらを提示して支払いを行うケースが一般的でした。しかし、スマホ決済を利用すれば、財布を取り出す必要なく、専用のアプリをスマートフォンにインストールし、事前に支払い情報を登録しておくだけで準備が完了します。
レジでアプリを起動して画面を提示したり、スマートフォン本体を専用の読み取り端末にかざしたりするだけで、瞬時に支払いが終わります。手軽さとスピード感が、スマホ決済が急速に普及している最大の理由と言われています。
また、物理的な現金のやり取りが発生しないため衛生的である点やポイント還元率が高く設定されているサービスが多い点も、利用者にとって大きなメリットでしょう。現代のキャッシュレス社会を象徴する決済手段であり、効率的に支払える方法です。
スマホ決済の種類は2つ!それぞれの方法について紹介
スマホ決済は「QRコード決済(コード決済)」と「タッチ決済(非接触型決済)」の二つに分けられます。QRコード決済では、スマートフォンのアプリ上に表示されるQRコードやバーコードを店員に読み取ってもらうか、利用者が店舗に設置されたQRコードを自身のスマートフォンで読み取ることで支払いを行う方法です。手軽に導入できるため、多くのお店で採用が進んでいます。
タッチ決済では、NFC(近距離無線通信規格)やFeliCa(フェリカ)といった技術を利用し、スマートフォン本体をレジにある専用の読み取り端末(リーダー)にかざすだけで支払いが完了する方式です。事前のアプリ起動が不要な場合も多く、スピーディな決済が可能です。いずれの方式も、スマートフォンが財布の代わりとなる点は共通していますが、利用シーンや対応端末、決済スピードが異なります。ここでは、スマホ決済の種類について解説します。
それぞれ順に解説いたします。
QRコード決済は手軽で利用者が最も多い
近年の日本においてスマホ決済の中で最も利用者が多いとされているのが、QRコード決済です。QRコード決済の特徴は手軽さが挙げられており、利用者は専用のアプリをダウンロードし、銀行口座やクレジットカードを登録するだけですぐに使い始められます。特別な設定や対応機種を気にする必要が少ない点も、普及を後押ししていると言えます。
支払い方式は、利用者がアプリでQRコードやバーコードを表示し店側がスキャナーで読み取る「ストアスキャン方式」と、利用者が店舗に掲示されたQRコードをアプリで読み取り金額を入力する「ユーザースキャン方式」の2種類が一般的です。
また、事業者側にとっても、高価な専用端末を導入せずとも、QRコードを印刷して設置するだけで対応できるため、導入コストが低いメリットがあります。そのため、大規模チェーン店だけでなく、個人経営の小規模な飲食店や小売店にも急速に普及しています。各社が実施する大規模なポイント還元キャンペーンも利用者を増やす要因となり、スマホ決済の代表的な決済手法と言えるでしょう。
主要なQRコード決済サービスを紹介
QRコード決済の市場には、多くの事業者が参入しており、主要とされる決済サービスは以下のとおりです。
- PayPay
- LINE Pay
- 楽天ペイ
- d払い
- au PAY
- メルペイ
QRコード決済サービスの代表格は「PayPay(ペイペイ)」です。ソフトバンクとヤフーの強力なバックボーンを持ち、頻繁に行われる大規模な還元キャンペーンやさまざまな施策で圧倒的なシェアを獲得しています。QRコード決済の使用率を調査したデータによると、全体の65.1%がPayPayを使用しています。
次に、コミュニケーションアプリ「LINE」を基盤とする「LINE Pay」も人気を集めています。日常的に使うアプリ内で決済が完結する利便性や、友人・知人への送金機能が特徴です。
また、ECサイト大手の楽天グループが提供する「楽天ペイ」も注目されています。楽天市場など楽天経済圏での利用で貯まる「楽天ポイント」を、そのまま別の支払いに使用できる点が強みです。さらに、NTTドコモが運営する「d払い」は、ドコモユーザー以外でも利用可能で「dポイント」が貯まる・使える点が支持されています。そのほかにも「au PAY」や「メルペイ」など、各社が独自のQRコード決済サービスを展開しています。
タッチ決済は端末をかざすだけで完了する非接触型
タッチ決済はNFC(Near Field Communication:近距離無線通信)と呼ばれる技術規格を使用し、日本では高速処理が可能な「FeliCa(フェリカ)」技術を搭載したスマートフォンを利用する支払い方法です。 タッチ決済の最大の魅力は、他の決済以上のスピードです。QRコード決済のように、事前にアプリを起動したり、コードを読み取ったりする必要がありません。対応するクレジットカードやデビットカード、交通系ICカードなどをスマートフォンの「ウォレット」機能(Apple Payや Google Payなど)に登録しておけば、レジでタッチ決済を選択し、スマートフォン本体を専用の読み取り端末にかざすだけで完結します。
圧倒的な速さは、混雑するコンビニエンスストアや駅の改札、自動販売機など、早い決済が求められる場面で人気を集めています。
iD・QUICPay・交通系ICの違いを解説
スマートフォンで利用できるタッチ決済の代表ブランドは、以下のとおりです。
- iD
- QUICPay
- 交通系IC
上記3つのブランドはすべてFeliCa技術を用いた非接触型決済を利用しています。それぞれ決済のタイミングに違いがあり、iDとQUICPayは、基本的に「ポストペイ型(後払い)」または「デビット型(即時払い)」です。スマートフォンに登録したクレジットカードやデビットカードと紐づいており、決済した金額は、後日そのカードの利用代金としてまとめて請求されるか、即時に銀行口座から引き落とされます。事前にチャージする手間が不要な点がメリットです。
一方、「交通系IC(SuicaやPASMOなど)」は、原則としてプリペイド型(前払い)です。利用するには、あらかじめスマートフォン内のSuicaやPASMOにクレジットカードなどから現金をチャージしておく必要があります。チャージした残高の範囲内でのみ決済が可能です。
スマホ決済のメリットはスピードと手軽さ
スマホ決済は現金を使用することなく、会計を手軽かつ瞬時に済ませられる点が特徴で利用時にはポイント還元やサービスごとのキャンペーンを活用できる可能性があります。決済後は利用履歴をデータ上で管理できるため、家計簿をつけている人にも最適です。サービスによっては個人間で送金もできるため、家族や友人間でもスムーズに利用できます。具体的なスマホ決済のメリットは、以下のとおりです。
それぞれ順に解説します。
スマホ決済は会計を瞬時に済ませられるスピード感が魅力
スマホ決済が持つメリットは、会計が完了するまでのスピード感です。従来の現金払いでは、財布から必要な金額の紙幣や小銭を探して取り出し、店員に渡し、お釣りを受け取るという一連の動作が必要でした。特に小銭が不足している場合や、レジが混雑している時には、やり取りがストレスになることも少なくありません。
また、クレジットカード払いもキャッシュレスではありますが、カードを端末に挿入したり、スライドさせたりした後、暗証番号の入力やサインを求められる場合があり、意外と時間がかかってしまいます。
一方、スマホ決済は圧倒的にスピーディです。QRコード決済であれば、アプリを起動してコードを提示するだけで完了します。タッチ決済では、対応端末にスマートフォン本体をかざすだけで、1秒足らずで決済が完了します。手軽さと速さは、日々の忙しい日常やビジネスシーンにおいて、最適な決済方法と言えるでしょう。
ポイント還元やキャンペーンでお得に利用できる
スマホ決済を利用するメリットとして、ポイント還元や各種キャンペーンの活用が挙げられます。多くのスマホ決済サービスは、利用者獲得のために独自のポイント還元システムを導入しています。現金で支払った場合、基本的にポイントは付きませんが、スマホ決済を利用するだけで、決済金額の0.5%や1.0%、時には1.5%といったポイントが自動的に還元されます。貯まったポイントは、次回の支払いに1ポイント=1円として利用できるため、実質的な割引を受けていることと同じと言えます。
また、各社が競って展開するキャンペーンも特徴です。例えば、「特定のチェーン店で利用すると最大20%還元」や「抽選で決済金額の全額が戻ってくる」といった大規模なプロモーションが頻繁に開催されています。これらのキャンペーンを活用すれば、現金払いや通常のクレジットカード払い以上の経済的なメリットが得られます。
スマホ決済の支払い元を特定のクレジットカードに設定することで、スマホ決済側のポイントとクレジットカード側のポイントを二重取りできるケースもあり、日々の買い物をお得に済ませられるでしょう。
利用履歴が管理しやすく家計簿などがつけやすい
スマホ決済は、利用履歴が確認できるため、日々の支出管理がしやすいメリットがあります。現金で支払いをすると、その都度レシートを受け取り、保管して家計簿に手入力するか、あるいはレシート自体を紛失して「何に使ったかわからないお金」が発生しがちです。
しかし、スマホ決済を利用すれば、すべての支払い履歴がスマートフォンのアプリ内に自動的に、かつリアルタイムで記録されます。いつ・どの店で・いくら支払ったかが時系列で一覧表示されるため、自分のお金の使い方を正確に把握することが可能です。
わざわざレシートを取っておく必要も、記憶を辿って家計簿をつける手間もありません。さらに、多くのスマホ決済アプリは、家計簿アプリとデータを連携させる機能も備えています。連携設定さえしておけば、決済情報が自動的に家計簿アプリに取り込まれ、食費・日用品・交通費などの項目に自動で分類・集計してくれます。そのため、面倒だった家計管理がほぼ全自動化され、お金の流れが可視化されることで、無駄遣いを減らす意識や節約へのモチベーション向上にもつながります。
アプリによっては個人間で送金できる
一部のスマホ決済アプリ(PayPayやLINE Payなど)には、ユーザー同士で残高を送り合う「個人間送金」機能が搭載されています。従来であれば、飲み会やランチの会計時に、幹事が一旦まとめて支払い、後で参加者から現金を集金するという手間が発生していました。しかし、送金機能を使えば、その場で1円単位まで正確な金額をスマートフォン操作だけで送金できます。銀行振込のように高額な手数料がかかることもなく、銀行の営業時間に関わらず24時間365日、瞬時に送金が完了します。
現金の持ち合わせがなくてもその場でやり取りが完結し、お金の貸し借りに関するストレスを大幅に軽減できます。友人へのちょっとした立て替え金の返済や共同購入したプレゼント代金の精算など、日常のささいなお金のやり取りをスムーズに解決できる非常に便利な機能と言えるでしょう。
スマホ決済のデメリットについて解説
スマホ決済は現金にはないメリットが多く存在する一方で、デメリットも考慮が必要です。スマホの紛失や不正利用によるセキュリティ面のリスク、スマホ決済を導入していない店舗での対応などに注意が必要です。スマホ決済の具体的なデメリットは、以下のとおりです。
それぞれ順に解説します。
紛失や不正利用などセキュリティ上のリスクがある
スマホ決済は便利な一方で、利便性と引き換えにセキュリティ上のリスクも抱えています。スマートフォン本体の紛失や盗難が発生し、第三者の手に渡り、画面ロックが突破されてしまうと、登録されているクレジットカードやチャージ残高が不正に利用される危険性が高まります。
また、物理的な紛失だけでなく、オンライン上でのリスクも存在します。例えば、金融機関や決済サービス事業者を装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトに誘導してIDやパスワードを盗み出すフィッシング詐欺の被害に遭うと、アカウントが乗っ取られる可能性があります。
さらに、悪意のあるアプリをインストールしてしまうことで、決済情報や個人情報が抜き取られるケースも考えられます。リスクに対処するため、利用者はスマートフォン自体に必ず強固な画面ロック(指紋認証や顔認証、パスコード)を設定し、決済アプリ側でも二段階認証を設定するなど、厳重な対策が不可欠です。
スマホ決済に対応していない店舗もある
スマホ決済は急速に普及し、大手チェーン店やコンビニエンスストアでは当たり前に利用できるようになりました。しかし、すべての店舗がスマホ決済に対応しているわけではありません。特に個人経営の小規模な飲食店や小売店、地方の商店街、昔ながらの個人商店などでは、導入コストや決済手数料の負担、ITリテラシーの問題から、現金のみで受けつけているケースも少なくありません。
また、自動販売機やコインパーキング、公共施設の券売機など、特定の機器では未対応のケースがあります。スマホ決済対応の場合でも、利用できるブランドが限られているケースがあります。そのため、利用者は常に利用可否を確認する必要があり、万が一に備えて現金やクレジットカードも持ち歩かなければならない場合もあると認識しておきましょう。
事業者側は導入コストと支払いタイムラグが発生する
スマホ決済は利用者にとってはメリットが多い一方、導入する事業者側には負担が存在します。特に導入コストと決済手数料が代表的で、利用者がQRコードを読み取る方式の場合、店舗側はQRコードを印刷して掲示するだけなので低コストで済みます。しかし、店舗側がコードを読み取るスキャナーや、タッチ決済用の専用読み取り端末を導入する場合、数万円程度の初期費用が発生します。さらに、現金払いでは発生しない決済手数料が売上ごとに1.5%~3%引かれるため、利益率がその分圧迫されます。
また、入金のタイムラグが発生します。現金決済であれば、売上は即座に手元の現金となります。しかし、スマホ決済の場合、売上が発生してから、決済事業者を通じて店舗の銀行口座に入金されるまでに一定の期間が必要です。月に1〜2回の場合もあり、タイムラグによって小規模事業者のキャッシュフローを悪化させる要因となる可能性があります。
スマホ決済の導入と設定方法
スマホ決済は利便性の高い決済手段ですが「どうやってスマホ決済を始めればいいかわからない」といった人も多いでしょう。スマホ決済の導入と設定方法は、以下のとおりです。
それぞれ順に解説します。
主要スマホ決済アプリは登録後すぐに利用を始められる
主要なスマホ決済アプリは、登録完了後すぐに利用を始められます。専用のアプリをApp StoreやGoogle Playストアからダウンロードし、簡単な登録作業を済ませるだけですぐに利用を開始できます。スマートフォン本体と本人確認や通知のために利用する電話番号(SMS認証ができるもの)メールアドレスがあれば基本的な登録は完了します。
アプリを起動すると、利用規約への同意を求められ、その後、携帯電話番号を入力します。番号宛に数桁の認証コードがSMS(ショートメッセージ)で送られてくるので、アプリ画面に入力します。SMS認証によって本人確認が完了し、アカウントが作成されます。ここまでで数分もかかりません。
すぐに友人から送金を受け取ったり、キャンペーンで付与されたポイントを利用したりできる状態になります。気になったタイミングですぐスタートできる手軽さが、スマホ決済の大きな魅力です。
QRコード決済は初期設定とチャージ方法を確認する
スマホ決済アプリの登録が完了したら、次に必要になるのが支払い方法の設定です。QRコード決済を利用する場合、アプリにお金を入れておく「チャージ」または支払い元となるクレジットカードや銀行口座の登録が必要です。
多くのQRコード決済で推奨されている方法は銀行口座の登録です。アプリ内の指示に従い、利用したい金融機関を選択し、口座番号や暗証番号などを入力して本人確認を行うと、口座が紐づけられます。登録が完了すれば、いつでも必要な時に銀行口座から直接チャージができるようになります。
また、クレジットカードを登録すれば、チャージの手間なく後払いで決済できる場合もあります。チャージ方法には多様な選択肢があり、登録した銀行口座やクレジットカードからのチャージ、コンビニエンスストアのATMによる現金チャージ、特定の金券ショップなどでチャージする方法があります。自身のライフスタイルに合わせて選択しましょう。
支払い方法は自分の利用目的に合わせて選ぶ
スマホ決済アプリに支払い情報を登録する際、自身の目的に合わせて支払い方法を選択しましょう。スマホ決済の支払い方式は、大きく分けて以下の3つに分けられます。
- 前払い
- 即時払い
- 後払い
前払いはあらかじめ銀行口座やATMからアプリの残高にチャージしておき、残高から支払う方式です。チャージした分しか使えないため、家計管理がしやすく、使いすぎを防ぎたい人に最適です。即時払いは銀行のデビットカードを紐づけ、決済すると同時に銀行口座から直接代金が引き落とされる方式です。後払いは、クレジットカードを紐づけて支払う方式です。決済した金額は、後日クレジットカードの利用代金としてまとめて請求されます。チャージの手間が一切かからないため利便性が高いものの、手元に現金がなくても使えてしまうため、支出管理には注意が必要です。どの方法が自分に合っているか、お金の使い方や管理のしやすさを考慮して選択しましょう。
スマホ決済を利用する際の注意点
スマートフォン一つで支払いが完了するスマホ決済は、利便性の高い決済方法です。しかし、手軽に利用できる一方で、利用する上で必ず理解しておくべきいくつかの注意点が存在します。注意点を把握しておかないと、思わぬトラブルや金銭的な被害に遭う可能性があります。特にセキュリティに関する問題は重要で、スマートフォンにはさまざまな情報が登録されているため、紛失や盗難、アカウントの乗っ取りによる不正利用のリスクと常に向き合う必要があります。
また、便利な決済方法もスマートフォンの電源が切れてしまうと利用できません。外出先でバッテリー切れを起こし、支払いができなくなる事態も想定が必要です。さらに、プリペイド型の決済サービスでは、レジに進んでから残高不足に気づくといった失敗も起こりがちです。スマホ決済を安全かつ快適に使いこなすためには、事前に適切な設定を行い、仕組みと注意点の理解が不可欠です。具体的にスマホ決済を利用する際の注意点は、以下のとおりです。
それぞれ順に解説します。
生体認証などセキュリティ設定を事前に完了させ安全性を高める
スマホ決済を利用する上で、最も優先して対策すべきはセキュリティの確保です。スマートフォンには決済情報やクレジットカード情報など、重要な個人情報が詰まっています。万が一、スマートフォンを紛失したり、盗難に遭ったりした場合、端末のロックが解かれると第三者に決済アプリを起動され、不正利用されてしまう危険性が高まります。最悪の事態を防ぐため、スマートフォン本体の画面ロックを確実に設定しましょう。
単純なパスコードだけでなく、可能であれば指紋認証や顔認証といった生体認証のせて位が必要です。他人が容易に突破できない、非常に強固なセキュリティ手段となります。
さらに、スマートフォン本体のロックだけでなく、決済アプリ自体にも個別にパスワードロックや起動時の生体認証を設定できる場合が多いので、二重の対策を講じておくことを強く推奨します。設定を事前に行っておくだけで、万が一の際の被害を最小限に抑えることができ、安心してスマホ決済の利用ができるでしょう。
チャージや入金方法を理解して残高不足を防ぐことが大切
スマホ決済の中でも、特にPayPayやLINE Pay、交通系ICといったプリペイド型のサービスを利用する際には、残高不足に注意が必要です。レジで支払おうとした際に、アプリの残高が足りず、決済がエラーになってしまうと対応に時間がかかります。結局、その場で慌ててチャージ操作をしたり、後ろに並んでいる人の視線を感じながら別の決済手段で支払う必要になったりします。スマホ決済の強みがなくなってしまいます。そのため、自身が利用している決済サービスのチャージ方法を正確に理解しておく必要があります。
銀行口座と紐づけて即時チャージできるように設定しておくのか、クレジットカードを登録しておくのか、コンビニのATMで現金チャージするのかなど、手段を把握しておきましょう。最も効果的な対策は、多くのサービスで提供されている「オートチャージ機能」がおすすめです。残高が一定金額を下回ったら、自動的に登録した口座やカードから一定額がチャージされるように設定しておけば、残高不足を心配する必要がなくなるでしょう。
スマホのバッテリーが切れてしまうと使用できなくなる
スマホ決済の利便性は、スマートフォンの充電がチャージされており、正常に動作することを前提にしています。スマートフォンのバッテリー切れは、スマホ決済における重要な注意点と言えます。QRコード決済だけではなく、FeliCaチップを利用するタッチ決済でも、スマートフォンの電源が完全に落ちてしまうと、決済機能は一切利用できなくなります。
例えば、外出先でスマートフォンの充電が切れてしまった場合、コンビニで買い物ができないだけでなく、駅の改札を通ることもできなくなり、生活が立ち行かなくなるリスクさえあります。
現金や物理カードを一切持たずにスマホ決済だけに依存していると、リスクが非常に深刻な問題です。そのため、モバイルバッテリーを常に携行する習慣をつけることがおすすめです。万が一充電が少なくなっても即座に対応できます。日頃からスマートフォンの充電を怠らないことはもちろんですが、リスク分散のために、最低限の現金や1枚のクレジットカードを財布に入れて持ち歩くことで安心してスマホ決済を利用できるでしょう。
スマホ決済は今後ますます普及が進む便利な支払い手段
以上、スマホ決済の概要から利用するメリット・デメリットを解説しました。
スマホ決済は年々普及しており、ユーザーだけではなく事業者側も対応するケースが増えています。スマホ決済は、会計を瞬時に済ませることができ、ポイント還元などの恩恵も受けられます。現金にはないメリットが多いものの、スマホ紛失やセキュリティリスク、充電切れなどの対策が必要です。
会計の利便性を高めるためにも、自身のライフスタイルに合わせて現金決済から少しずつスマホ決済に移行すると良いでしょう。