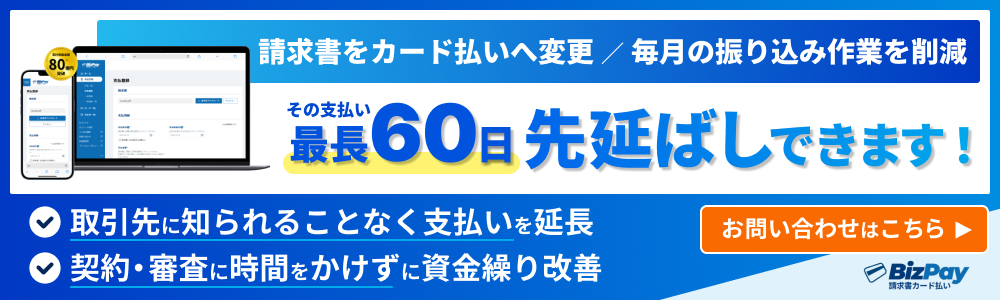日本国内でQRコード決済サービスが急速に普及する中、複数のQRコードステッカーが店頭に並ぶ光景を目にすることが増えてきました。こうした状況を改善するため、総務省と経済産業省が中心となって推進されているのが統一QRコード規格「JPQR」です。
一般社団法人キャッシュレス推進協議会によって策定されたこの統一規格は、一枚のQRコードで複数のQR決済サービスに対応できる仕組みとして注目されています。
本記事では、JPQRの基本的な仕組みから導入のメリットやデメリット、実際の申込方法まで、企業や店舗のご担当者にとって必要な情報を詳しく解説していきます。
JPQRとは総務省が推進する複数決済対応の統一QRコード規格
JPQRは2019年3月に一般社団法人キャッシュレス推進協議会によって仕様が策定された、QRコード決済用の統一規格です。総務省と経済産業省がオブザーバーとして関与し、国を挙げた取り組みとして進められてきました。
当時、政府は2025年までにキャッシュレス決済比率を40%程度に引き上げる目標を掲げており、この目標は2024年に前倒しで達成されています。QRコード決済は相対的に低い手数料で利用できるサービスも多く、特に中小規模の店舗にとって導入しやすい決済手段として期待されています。
JPQRは乱立するQR決済を統一し普及促進を目的に誕生
QRコード決済サービスが国内で広がる中、各事業者が独自のQRコード規格を採用したことで、店舗側には深刻な課題が生じていました。複数のサービスに対応しようとすると、それぞれ異なるQRコードステッカーを店頭に掲示する必要があり、レジ周りがQRコードで埋め尽くされてしまう状況が発生していたのです。小規模店舗では物理的にすべてのサービスに対応することが困難なケースもありました。
各決済サービスへの申し込み手続きも個別に行う必要があり、事務的な負担も相当なものでした。新しいサービスを導入するたびに、それぞれの事業者と契約を結び、審査を受け、管理画面の使い方を習得する必要がありました。こうした煩雑さが、人手に余裕のない中小規模の事業者にとって大きな障壁となっていました。
JPQRはこうした問題を根本から解決するために誕生した統一規格です。複数のQRコード決済サービスを一つのQRコードに集約することで、店頭のステッカーは一枚で済むようになります。また、申し込み手続きも一本化され、一度の申請で複数の決済サービスへ同時に加盟店申請を行えます。一般社団法人キャッシュレス推進協議会は、グローバルスタンダードに準拠する形で仕様を定めており、将来的な国際的な相互運用性も視野に入れた設計となっています。
JPQR導入で事業者と利用者双方が得られるメリットを解説
JPQRの導入は、店舗側と利用者側の双方に具体的なメリットをもたらします。従来の個別対応型のQRコード決済では解決できなかった課題を、統一規格という新しいアプローチで解消しようとする試みです。
店舗側にとっては業務効率化とコスト削減、利用者側にとっては決済の利便性向上が期待できます。
メリットについてそれぞれ順に解説いたします。
店舗はJPQR導入で複数QR決済を一括で受付け可能
店舗側にとってJPQRの最大のメリットは、複数のQR決済サービスを一つのQRコードで受け付けられることです。従来は決済サービスごとに異なるステッカーをレジ周辺に掲示する必要がありましたが、JPQRなら一枚で済むため、店頭がすっきりと整理されます。
申し込み手続きの簡略化も重要なポイントです。JPQRの専用受付システムを通じて一度の申請を行うだけで、希望する複数の決済サービスへ同時に加盟店申請ができます。各サービス事業者と個別に契約する手間がなくなり、事務作業の負担が大幅に軽減されます。
JPQRには専用の売上管理画面が提供されており、導入している複数の決済サービスの売上情報を一元管理できます。従来は各サービスごとに異なる管理画面で売上を確認する必要がありましたが、一つの画面でまとめて確認できるため、経理業務の効率化につながります。導入費用や維持費用が原則として無料である点も大きな魅力です。
利用者はJPQRでアプリを選ばず多様なQR決済が利用可能
利用者にとってのメリットは、自分が日常的に使っている決済アプリをより多くの店舗で利用できるようになることです。JPQRに対応した店舗では、au PAYやd払い、楽天ペイ、メルペイなど、複数の主要なQR決済サービスが使える可能性が高まります。
決済手続きもシンプルです。店舗提示型の場合、店頭に掲示されているJPQRのQRコードを自分の決済アプリで読み取るだけで完了します。どの決済サービスのアプリを使っても同じコードを読み取れるため、利用者は特に意識することなくスムーズに会計を済ませられます。
JPQRはキャッシュレス普及を促進し社会全体の利便性を高める
JPQRの普及は、個々の店舗や利用者だけでなく、日本社会全体のキャッシュレス化推進にも寄与する可能性を持っています。現金決済中心の社会からキャッシュレス社会への移行は、業務効率化や生産性向上といった経済的メリットをもたらします。現金を扱う店舗では、レジ締め作業や金銭管理、銀行への入金作業などに時間と人手がかかりますが、キャッシュレス決済が普及すれば、こうした業務負担が軽減されます。
衛生面でのメリットも見逃せません。新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、非接触型の決済手段への関心が高まりました。現金の受け渡しを減らせるキャッシュレス決済は、感染症対策の観点からも推奨されています。JPQRのようなQRコード決済は、専用端末が不要で非接触での決済が可能です。
インバウンド需要への対応という視点も重要です。訪日外国人観光客の多くは、自国でキャッシュレス決済に慣れ親しんでおり、日本でもキャッシュレスで買い物をしたいというニーズがあります。JPQRの規格はグローバルスタンダードに準拠しているため、将来的にはアジア諸国との相互運用も視野に入れられています。
JPQR導入に伴うデメリットや注意点を紹介
JPQRには多くのメリットがある一方で、実際に導入を検討する際には注意すべき点やデメリットも存在します。特に手数料の取り扱いや入金サイクルは各決済サービスによって条件が異なるため、事前に確認しておく必要があります。
また、現時点での普及状況や大手決済サービスとの関係性なども、導入判断において考慮すべき重要なポイントです。
デメリットについてそれぞれ順に解説いたします。
決済手数料や入金サイクルが事業者ごとに異なる点
JPQRの大きな注意点は、申し込みとQRコード発行は統一されているものの、決済手数料や入金サイクルについては各決済サービス事業者の条件がそのまま適用されることです。JPQRはあくまで「統一QRコード」と「一括申し込み窓口」を提供する仕組みであり、各決済サービスとの契約条件自体は個別に設定されています。
決済手数料は事業者によって無料のものから3パーセント程度のものまで幅広く設定されています。クレジットカード決済の手数料が一般的に3から6パーセント程度であることと比較すれば相対的に低い水準ですが、どの決済サービスを選ぶかによって店舗側の負担は大きく変わってきます。
入金サイクルも事業者ごとに異なります。早いサービスでは最短で翌銀行営業日に入金されるものもあれば、月に1回から2回程度の入金となるサービスもあります。複数の決済サービスを同時に導入した場合、それぞれ異なる手数料率と入金サイクルで運用されるため、管理が複雑になる側面があります。
加盟店舗数が少なく利用できる場所が限定されている
JPQRの普及状況については、当初の期待ほどには進んでいないという現実があります。総務省が2019年度から推進してきたJPQR普及事業では、2021年度末までに10万店舗への導入を目標としていましたが、実際の普及率は期待を大きく下回る結果となりました。報道によれば、2021年時点でのJPQR普及率は約1.5パーセント程度にとどまっていたとされています。
総務省は2021年度で普及促進事業を終了し、2022年度以降は一般社団法人キャッシュレス推進協議会が主体となって運営を引き継いでいます。国主導の強力な推進体制から民間主体の運営に移行したことで、普及のペースがさらに鈍化する懸念もあります。現状では、JPQRが導入されている店舗はまだ限定的であり、利用者が広く認知している状況にはなっていません。
PayPayやd払いなど大手QR決済との競合が普及の妨げになる
JPQR普及の最大の障壁となっているのが、大手QR決済サービス事業者の戦略との競合です。特にQRコード決済市場で圧倒的なシェアを持つPayPayの動きは、JPQR普及に大きな影響を与えています。PayPayは2020年当時、自社で独自に開拓した加盟店とJPQR経由で加盟した店舗とで、手数料に明確な差をつける方針を打ち出しました。
当時、PayPayが直接契約した店舗については手数料を無料としていた一方で、JPQR経由で申し込んだ店舗については有料の手数料設定としました。この手数料格差戦略により、店舗側としてはJPQRを経由するよりもPayPayと直接契約したほうが有利という状況が生まれました。なお、2025年現在、PayPayの直接契約店舗の手数料も有料化されていますが、JPQR経由との手数料差は依然として残っています。
決済サービス事業者の立場からすれば、こうした戦略は自社の顧客基盤を守り、囲い込みを強化するための合理的な判断といえます。コストをかけて開拓した加盟店ネットワークを、統一規格によって他社と共有することは、競争上の優位性を失うことにつながりかねません。一方で、こうした大手事業者の戦略は、キャッシュレス決済の裾野拡大という政策目標とは相反する側面があります。
JPQRと他のQRコード決済の違いについて解説
JPQRと通常の個別QRコード決済サービスとの違いを理解することは、導入を検討する上で重要です。両者は決済の仕組み自体は同じQRコードを使用しますが、申し込み方法や管理の仕方、実際の運用面で異なる特徴を持っています。
ここでは、統一QRコードであるJPQRと、各社が独自に提供しているQRコード決済サービスとの具体的な違いについて解説します。
統一QRコードの導入で複数サービスを一つにまとめられる
JPQRと個別のQRコード決済サービスの最も大きな違いは、一つのQRコードで複数の決済サービスに対応できる点です。通常、各決済サービス事業者と個別に契約した場合、サービスごとに異なるQRコードを店頭に掲示する必要があります。これに対してJPQRでは、一枚の統一QRコードで、導入を選択したすべての決済サービスに対応できます。
この違いは、店舗運営の実務面で大きな差となって現れます。個別契約の場合、複数のステッカーやポスターを掲示する必要があり、小規模店舗では掲示スペースに限りがあります。一方、JPQRであれば一枚のステッカーで済むため、店頭がすっきりと整理されます。従業員への教育負担という点でも、JPQRの場合は顧客が自分の好きな決済アプリで統一QRコードを読み取るだけで決済が完了するため、負担が軽減されます。
ただし、実際に利用できる決済サービスの範囲については注意が必要です。店舗がJPQRを導入した際にどの決済サービスを選択したかによって、実際に使えるサービスは店舗ごとに異なります。JPQR対応店舗であっても、すべてのJPQR対応決済サービスが使えるとは限りません。
各サービスごとに決済手数料や導入条件が異なる点に注意
JPQRを導入する際の重要な注意点として、決済手数料や導入条件は各決済サービス事業者が個別に設定しているという点があります。JPQRはあくまで申し込み窓口を一本化し、統一QRコードを提供する仕組みであり、各決済サービスとの契約条件そのものを統一するものではありません。
決済手数料について見ると、JPQR経由で申し込んだ場合の手数料率は決済サービスごとに大きく異なります。一部のサービスでは無料期間を設けているものもあれば、最初から2パーセントから3パーセント程度の手数料を設定しているサービスもあります。審査基準も各決済サービス事業者が独自に設定しています。JPQRを通じて一括で申し込みを行っても、その後の審査は各事業者が個別に実施するため、すべてのサービスに必ず加盟できるわけではありません。
導入後の各種手続きについても、各決済サービスごとに対応する必要があります。入金口座の変更や契約内容の変更、解約といった手続きは、JPQR側では対応しておらず、各決済サービスの管理画面から個別に行わなければなりません。
普及が進まない理由は事業者間競合と利用店舗数の少なさ
JPQRの普及が当初の計画通りに進んでいない背景には、複数の構造的な要因が絡み合っています。最も大きな要因は、QRコード決済市場における競争環境の変化です。JPQR構想が策定された当時は、多数の決済サービスが乱立していましたが、その後PayPayが積極的なキャンペーンや加盟店開拓を通じて圧倒的なシェアを獲得しました。すでに大きなシェアを持つ事業者にとって、統一規格を通じて競合他社と加盟店を共有することは、自社の競争優位性を損なうリスクがあります。
店舗側の視点から見ると、利用可能店舗数の少なさも普及を妨げる要因です。新しい決済手段を導入する際、店舗が最も気にするのは「どれだけの顧客が実際に使ってくれるか」という点です。JPQRを導入しても、周辺の店舗がほとんど導入していない状況では、実際の利用につながりにくいという悪循環が生じています。
コロナ禍による影響も無視できません。JPQRの全国展開が本格化した2020年度は、新型コロナウイルス感染症の流行と重なり、対面での説明会やイベントが制限されました。また、総務省は2019年度から2021年度までの3年間で約20億円の予算を投じて普及事業を推進しましたが、2022年度からは民間主体の運営に移行したことで、普及活動の勢いが減速した面があります。
JPQR導入方法と申し込みから利用開始までの流れを紹介
実際にJPQRを導入する際の具体的な手順について解説します。JPQRの申し込みは専用のWebサイトから行え、法人だけでなく個人事業主も申請可能です。申し込みから実際に店舗でJPQRを利用できるようになるまでには、いくつかのステップがあります。必要な書類の準備から審査、QRコードステッカーの受け取りまで、一連の流れを把握しておくことで、スムーズな導入が可能になります。
それぞれ順に紹介します。
JPQR導入は申込書提出と審査完了で利用開始できる
JPQRの導入手続きは、現在は一般社団法人キャッシュレス推進協議会が運営するJPQR総合情報サイトから行えます。まず、サイトにアクセスして、利用規約や各決済サービスの契約条件を確認します。この段階で、どの決済サービスを導入するかを検討しておくことが重要です。各サービスの手数料率や入金サイクル、審査基準などの情報も公開されています。
申し込み手続きでは、事業者情報や店舗情報を入力し、必要書類をアップロードします。個人事業主の場合、本人確認書類として運転免許証またはパスポートが必要となります。マイナンバーカードは本人確認書類として認められていない点に注意が必要です。法人の場合も、代表者の本人確認書類が求められます。
申し込みが完了すると、選択した各決済サービス事業者による個別の審査が開始されます。審査期間は事業者によって異なりますが、通常は数日から数週間程度かかります。審査に通過した決済サービスから順次、契約手続きが進められます。審査が完了し契約が成立すると、JPQRのステッカーキットが店舗に送付されます。ステッカーを店舗のレジ周辺などに掲示すれば、すぐにJPQRでの決済受付が可能になります。
法人や個人事業主向けに用意された導入プランがある
JPQRは法人だけでなく、個人事業主も申し込める制度設計となっています。小規模な飲食店や小売店、サービス業など、さまざまな業種の事業者が導入対象となります。特に従業員が少ない小規模事業者にとって、複数の決済サービスに個別に申し込む手間を省けるJPQRの一括申し込みの仕組みは、大きなメリットとなります。
法人として申し込む場合、法人の登記情報や代表者情報、事業内容を示す書類などが必要になります。複数店舗を運営している場合でも、一括して申し込むことが可能です。個人事業主の場合は、事業を営んでいることを証明する書類や、本人確認書類が主な必要書類となります。ただし、各決済サービス事業者の審査基準は異なるため、事業形態によっては一部のサービスの審査で承認されないケースもあります。
一部のケースではJPQRを無料で導入して利用可能になる
JPQRの大きな魅力の一つは、導入費用や維持費用が原則として無料である点です。クレジットカード決済を導入する場合、専用の読み取り端末を購入する必要がありますが、JPQRはQRコードステッカーを掲示するだけで済むため、初期投資をほぼゼロに抑えられます。
月額の維持費用も基本的に発生しません。実際に決済が行われた際に、各決済サービスの手数料が発生するだけです。売上がない月には手数料の支払いも発生しないため、リスクを最小限に抑えて導入できます。JPQRのQRコードステッカー自体も無料で提供されます。ステッカーが破損したり紛失したりした場合でも、無料で再発行を申請できます。
ただし、完全に無料で運用できるかというと、いくつか注意すべき点があります。各決済サービスの決済手数料は当然発生します。手数料率は決済サービスごとに異なり、無料期間を設けているサービスもあれば、最初から手数料が発生するサービスもあります。また、一部の決済サービスでは、入金時に振込手数料が発生する場合があります。決済の入金確認や売上管理にはインターネット接続可能な端末が必要ですので、その点も考慮が必要です。
総務省が進めるJPQRだが現状はメリットと課題が共存している
JPQRは、総務省と経済産業省が推進し、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が策定した統一QRコード規格として、日本のキャッシュレス化推進において重要な役割を担うことが期待されていました。複数のQRコード決済サービスを一つのQRコードで受け付けられるという基本コンセプトは、店舗側の導入負担を軽減し、利用者側の利便性を向上させるという点で、理論的には非常に優れた仕組みです。一括申し込みの手軽さや、導入費用・維持費用が無料である点、店頭がすっきりと整理できる点など、多くのメリットが存在します。
しかし、現実の普及状況を見ると、当初の目標には遠く及んでいません。大手決済サービス事業者が自社の競争戦略を優先し、JPQR経由での契約を積極的に推進しない姿勢を取ったことが、普及の大きな障壁となりました。普及率が低いことで利用可能店舗が増えず、利用者側の認知度も高まらないという悪循環が生じています。決済手数料や入金サイクルが各決済サービスによって異なることも、管理面での複雑さを生んでいます。
それでも、JPQRが持つ潜在的な価値は失われていません。特に小規模事業者にとって、初期投資を抑えながら複数の決済サービスに対応できる仕組みは、依然として魅力的な選択肢です。今後、地域単位での集中的な導入促進や、自治体との連携による普及活動が展開されれば、利用可能店舗が一定数を超えた段階でネットワーク効果が働き、急速に普及が進む可能性も残されています。
キャッシュレス化という大きな流れの中で、JPQRは一つの選択肢として位置づけられています。PayPayなどの大手サービスと直接契約するのか、JPQRを通じて複数サービスに一括対応するのか、あるいは両方を組み合わせるのか。事業者はそれぞれの状況に応じて最適な選択をすることが求められます。JPQRの今後は、こうした市場の自然な淘汰と選択の中で決まっていくことになるでしょう。総務省が当初描いた理想像の実現には至っていませんが、キャッシュレス社会への移行を支える仕組みの一つとして、その役割を果たし続けています。